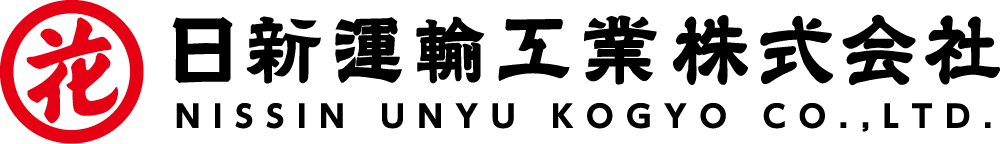物流関連二法について、詳しく知りたいと考えている事業者の方も多いのではないでしょうか。物流関連二法は2025年4月に改正され、事業者の対応が必要な場合があります。
この記事では、物流関連二法について詳しく解説します。改正の背景や事業者への影響にも触れるので、ぜひ内容を確認してみてください。
現在弊社では「物流コスト削減のための無料診断」を行っております。
昨今の人件費や燃料費の高騰で困っている場合は、コスト見直しをしてみませんか?
場合によっては物流費用の削減が可能な場合があるため、以下よりお気軽にお問い合わせください。

物流関連二法とは?
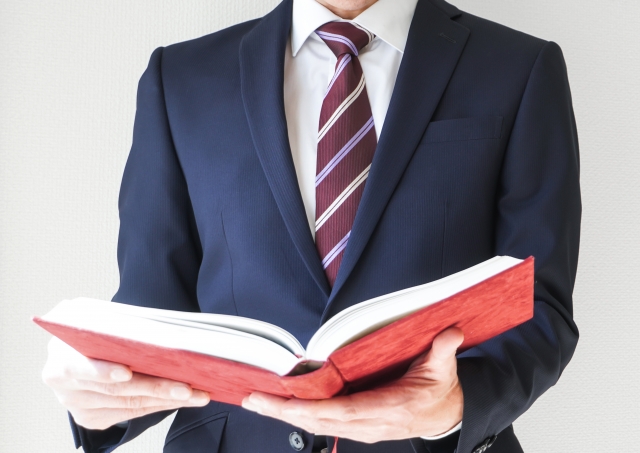
物流関連二法とは、以下の2つの法律です。
- 物流総合効率化法(流通業務総合効率化法)
- 貨物自動車運送事業法
それぞれについて、概要を確認していきましょう。
物流総合効率化法(流通業務総合効率化法)
物流総合効率化法(流通業務総合効率化法)は、物流業界の業務効率化と課題解決を目的とした法律です。正式名称は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」です。
物流総合効率化法では、事業者の義務や事業者への規制、国の支援措置が定められています。特に、事業者が作成する「総合効率化計画」の認定について定めることで、認定された事業者が国から様々な支援措置を受けることができ、物流業界の課題解決への貢献が期待されます。
物流総合効率化法で重要視されている課題は以下の3つです。
- トラックドライバー不足
- 長時間労働
- 地球温暖化
法で定められる業務の効率化によって、トラックドライバーの負担軽減や労働環境の改善ができ、労働力不足への対応が可能になります。地球温暖化をはじめとする環境問題の改善には、モーダルシフトなどを促進することで、二酸化炭素の排出量削減を目指しています。
貨物自動車運送事業法
貨物自動車運送事業法は、トラックをはじめとする自動車を使用した運送業の適正な運用や、輸送の安全性を向上させるための法律です。事業の種類や規制、許可や届出に関する事項が定められています。
貨物自動車運送事業法では、自動車を使用する運送業者を以下の表のように分類しています。
| 事業者の種類 | 説明 | 必要な許可・届出 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 一般的なトラック運送業者のように、不特定多数の荷主から依頼を受けて貨物を運送する事業。 | 原則、国土交通大臣の許可が必要 |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の1社の荷主から依頼を受けて、専属的に貨物を運送する事業。 | 原則、国土交通大臣の許可が必要 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽自動車や二輪自動車(125cc超)を使って貨物を運送する事業。 | 届出制 |
事業の種類を明確に分類することで、適切な規制を行い、輸送の安全性を向上させることが可能です。例えば、貨物軽自動車運送事業は、個人宅などへの少量の貨物輸送を担っているため、1人でも開業することができます。一方、より大きなトラックでたくさんの荷物を運ぶ一般貨物自動車運送事業は、最低5人のドライバーと1人の運行管理者が必要となり、より厳しい安全性が求められます。
物流総合効率化法の改正内容

物流総合効率化法は、働き方改革関連法によってトラックドライバーの人手不足が懸念されている、いわゆる「2024年問題」に対応するために改正されました。以前までは事業者への支援が主な目的でしたが、改正後は物流をより効率的にするために、荷主と物流事業者の責任を強化しています。
物流総合効率化法の改正内容は、主に以下の3つです。
- 荷主・物流事業者への規制を強化する
- 特定事業者への義務付けを強化する
- 物流統括管理者を選任させる
それぞれについて詳しく解説していきます。
荷主・物流事業者への規制を強化する
物流総合効率化法の改正で最も重要なのは、荷主と物流事業者への規制が強化されたことです。物流の効率化や環境負荷を抑えるための指導、助言を、国が今まで以上に行えるようになりました。
これまでは、国は事業者が申請する計画を認定することが前提でしたが、法改正後は物流の効率化への取り組みが不十分な事業者に対して国が指導できます。具体的には、以下のような措置をとることが可能です。
- 物流効率化の目標設定や計画策定の指導
- 運賃や料金の適正化に向けた助言
- 荷待ち・荷役時間の削減に関する改善勧告
国がより厳しい措置をとることで、物流の非効率性を正し、物流の問題を国が積極的に改善していけます。
特定事業者への義務付けを強化する
物流総合効率化法の改正内容には、特定事業者への義務付けの強化も挙げられます。一定以上の規模を持つ荷主と物流事業者に対して新たな義務を課すことで、物流業界全体の変革を促す目的があります。
特定事業者に課される義務は、以下のとおりです。
- 中長期計画の策定・公表
物流効率化や脱炭素化に関する具体的な目標と、それを達成するための中長期計画を策定し、公表しなければならない。 - 国への定期報告
計画の進捗状況や実績を、定期的に国に報告しなければならない。 - 国の指導・公表
報告した内容が不十分とされた時は、国から指導を受けその内容が公表される可能性がある。
大きな事業者に義務を課すことで、協力会社とも協力しながら効率化を進められ、物流業界全体に及ぼす影響が大きいです。
物流統括管理者を選任させる
物流統括管理者を選任させることも、物流総合効率化法の改正内容の1つです。荷主企業は物流統括管理者を選任することで、組織全体で物流効率化の取り組みを推進できます。
物流統括管理者の役割は、以下の4つです。
- 物流効率化計画の策定と実行
- 関係部署との調整
- 外部の物流事業者との連携
- 国への報告業務
物流統括管理者は物流の専門家なので、社内に1人いることで実効性の高い効率化策を実行しやすくなります。荷主企業の経営層の意識も高まり、物流を単なるコストではなく、経営戦略上の重要な要素として捉えるようにする効果も期待されます。
貨物自動車運送事業法の改正内容
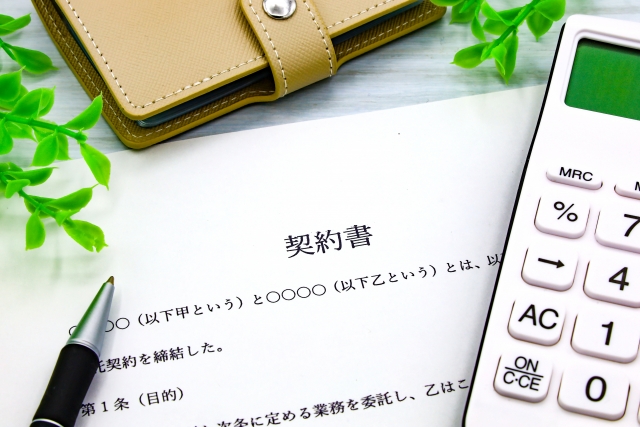
貨物自動車運送事業法も、「2024年問題」に対応するために改正されました。特に自動車輸送の事業を健全化し、人手不足でも安全性を確保しながら適正な事業を行うことが目的です。
貨物自動車運送事業法の改正内容は、主に以下の3つです。
- 取引の適正化を推進する
- 「実運送体制管理簿」を作成・保存させる
- 軽トラック運送業の安全性を強化する
それぞれについて、詳細を見ていきましょう。
取引の適正化と透明化を推進する
改正された貨物自動車運送事業法では、取引の適正化と透明化を推進する内容があります。運送事業者と荷主間の取引を適正化するため、以下の措置が義務化されました。
- 運送契約書面の交付義務
運送事業者には、運送契約を締結する際に運賃や料金、附帯業務料を明記した書面の交付が義務付けられました。口頭での曖昧な契約を防ぎ、トラブルを未然に防止することが目的です。 - 標準運賃の公示
国土交通省が標準的な運賃を公示することで、適正な運賃や料金収受を促します。
標準運賃を運送事業者が活用することで、健全な運送事業経営が期待されます。
契約書面の交付義務と標準運賃の公示で、不当に安い運賃や料金での取引をなくすことが改正の目的です。取引が適正化・透明化されることで、ドライバーの労働環境改善や安全確保に必要なコストを確保できます。
「実運送体制管理簿」を作成・保存させる
「実運送体制管理簿」を作成・保存させることも、貨物自動車運送事業法の改正内容の1つです。物流業界では多重下請け構造が常態化しているため、管理簿を使って輸送時の責任の所在を明確にします。
後から確認した時に責任の所在が分かるよう管理簿に記載しておくことで、安全管理体制の向上が期待できます。それぞれの事業者が責任を明確に背負うので、安全管理の意識が高まり、サプライチェーン全体での安全性確保が可能です。
実運送体制管理簿を作成する義務があるのは、荷主から直接依頼を受けた元請けの運送事業者です。実際に運送を行う事業者(実運送事業者)の氏名や名称、連絡先、請負階層などを記載します。
軽トラック運送業の安全性を強化する
貨物自動車運送事業法の改正では、軽トラック運送業の安全性も強化されました。近年のネットショッピングの普及で増えた、軽トラック運送業者の事故や労働問題に対応するために、法律の内容が見直されました。
軽トラック事業者に対する内容で変わった点は、以下の3つです。
- 一定規模以上の事業所における運行管理者の選任義務
- 重大な事故が発生した場合の国への報告義務
- 安全管理が不十分な事業者への行政処分
義務が課せられたり行政処分の対象となったりすることで、軽トラック事業者はより計画的で安全な運行体制を構築せざるを得なくなります。無理な運行計画の見直しや、ドライバーの健康状態の管理などが徹底され、事故のリスクが減少する上に労働環境の改善も期待できます。
物流関連二法はどうして改正された?

物流関連二法は、日本の物流業界が直面する課題に対応するために改正されました。具体的には、主に以下の3つが理由として挙げられます。
- 2024年問題に対応するため
- 多層下請け構造による問題を解決するため
- 物流をさらに効率化するため
それぞれについて、詳細を解説していきます。
2024年問題に対応するため
物流関連二法が改正された最大の理由は、「2024年問題」への対応です。「2024年問題」に対応するため、労働環境の改善と効率的な輸送ができるように法律が改正されました。
「2024年問題」は、2024年4月から適用された労働時間の新基準により、人手不足や輸送能力の低下による輸送遅延などの問題が起こる可能性が高まる問題です。ドライバーの長時間労働は是正される一方、輸送能力の低下や運賃の高騰が懸念されています。法改正によって、ドライバーの労働時間短縮だけでなく、物流機能も維持することを目指しています。
多層下請け構造による問題を解決するため
多層下請け構造による問題を解決することも、物流関連二法改正の重要な目的です。物流業界に深く根付く多層下請け構造では、元請けから下請け、孫請けへと仕事が流れる過程で、運賃が安くなります。その結果、末端のドライバーの収入が減少し、長時間労働や過積載の温床となっていました。
改正法では、この問題を解決するために、実際に荷物を運ぶ事業者を明確にする書類を作成させたり、運賃や料金を明確にした書面を交付させたりしています。書類として明確に記録することで、適正な運賃が末端まで行き渡り、ドライバーの労働環境改善と安全確保につながることが期待できます。
物流をさらに効率化するため
物流関連二法改正の理由には、物流をさらに効率化することも挙げられます。運送事業者だけでなく荷主企業も積極的に関与し、サプライチェーン全体で物流の非効率を解消することが必要です。
物流業界では、積載率の低さや長時間にわたる荷待ちなどの非効率な慣行があり、コストの増加や二酸化炭素排出量増加の原因となっています。運送業者に任せるだけでなく荷主企業も協力することで、さらなる効率化を目指しています。
物流のことなら日新運輸工業におまかせください

日新運輸工業では、トラック輸送の業務委託やアウトソーシングを受注しております。運送のプロなので、物流関連二法の改正に適応しながら、より効率的な物流を行います。トラック輸送だけでなく、フェリー輸送や鉄道輸送も行っているので、モーダルシフトも考慮した運送方法のご提案が可能です。
輸送関連二法に適した物流をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。電話やメールにて、見積もり・お問い合わせを承っております。
国内貨物輸送の手間やコストにお困りの人は、日新運輸工業におまかせください!
以下サービスページより国内貨物輸送の問い合わせができますので、ご相談お待ちしております。
まとめ

この記事では、物流関連二法について解説しました。物流関連二法とは、物流総合効率化法と貨物自動車運送事業法のことで、物流の効率化と安全性を高めるために必要な法律です。
物流関連二法の改正内容は以下のとおりです。
- 物流総合効率化法
- 荷主・物流事業者への規制を強化する
- 特定事業者への義務付けを強化する
- 物流統括管理者を選任させる
- 貨物自動車運送事業法
- 取引の適正化と透明化を推進する
- 「実運送体制管理簿」を作成・保存させる
- 軽トラック運送業の安全性を強化する
改正により、物流業界全体の運営改善が期待されますが、事業者は背負う義務が増えました。改正の目的を理解して義務を遂行し、物流業界の効率化と安全性向上に貢献しましょう。
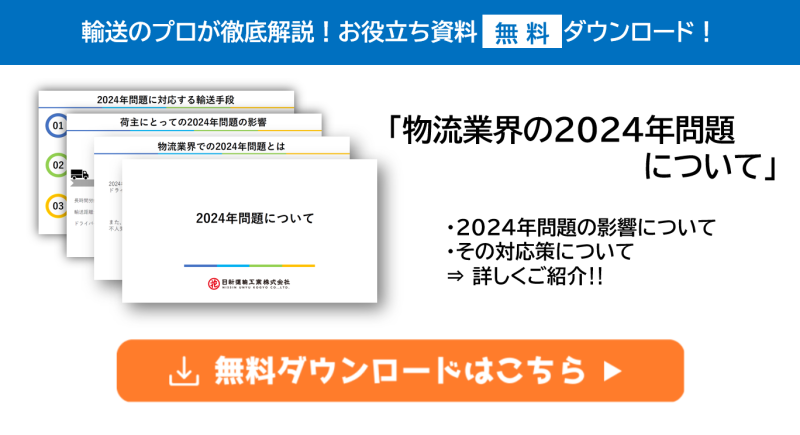
監修者
浜田 智弘
日新運輸工業株式会社 運輸部 部長
国内物流の現場で指揮を執り、トラック・鉄道・フェリーを組み合わせた最適な輸送提案や、「2024年問題」への実務対応に精通。「マルハナジャーナル」での執筆を通じ、物流業界の課題解決にも尽力している。「感謝と恩返し」を信念に、困難な物流課題にも粘り強く向き合い続けている。