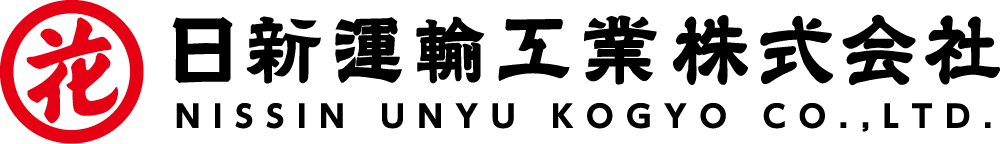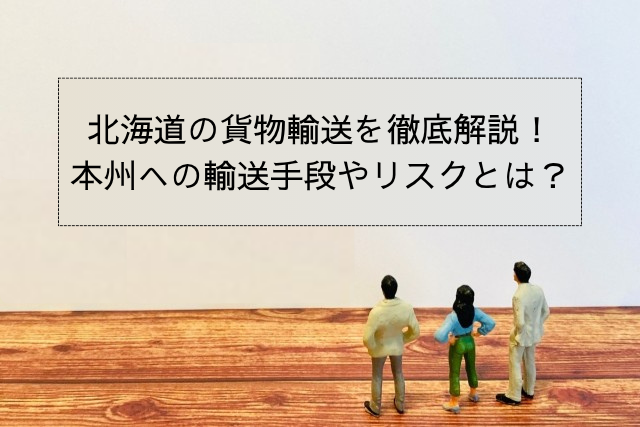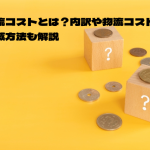北海道の貨物輸送について知りたい人も多いのではないでしょうか。北海道では広大な土地ならではの確立された輸送手段があります。
この記事では、北海道の輸送手段について解説します。本州への輸送手段やリスクについても解説するので、ぜひ内容を確認してみてください。

北海道における輸送の特徴

北海道における輸送の特徴には、以下の3つがあります。
- 複数の輸送手段を組み合わせる
- 鮮度を保つ必要性が高い
- 大量に輸送する
それぞれについて詳しく解説していきます。
複数の輸送手段を組み合わせる
北海道の輸送手段の特徴には、複数の輸送手段を組み合わせることが挙げられます。北海道は土地が広く都市や集落が点在している上に、本州とも離れているので、トラックやフェリー、鉄道を組み合わせた輸送手段が主流です。
例えば、本州から北海道へ送られる物資は、まずフェリーや鉄道を利用して輸送されます。長距離輸送では、トラック単独で輸送するよりもフェリーや鉄道を利用した方が物流のコスト効率がよいでしょう。青函トンネルを通る鉄道コンテナや、苫小牧や小樽などと本州を結ぶ大型フェリーが運行しています。
北海道に到着した貨物はトラックに積み替えられ、道内各地に運ばれます。フェリーや鉄道がアクセスできない地域にはトラックを使うことで、柔軟な輸送が可能です。それぞれの輸送手段の強みを最大限に活かし、効率的なサプライチェーンを構築することが、北海道における輸送の特徴です。
鮮度を保つ必要性が高い
鮮度を保つ必要性が高いことも、北海道における輸送の特徴です。北海道の主要な輸出品目である海産物や農産物は、鮮度が商品価値を大きく左右するため、迅速な輸送が最大の課題です。
特に、ウニやカニ、メロン、アスパラガスといった高付加価値の生鮮食品は、収穫・水揚げから24時間以内に消費地に届ける必要があります。一般的には、保冷設備を備えた航空貨物便を利用し、新千歳空港から羽田空港などへ空輸されます。
ジャガイモやタマネギ、カボチャといった比較的日持ちする農産物や、冷凍加工された水産物などは、主にフェリーや鉄道を利用するのが主流です。航空便に比べるとフェリーや鉄道は輸送コストが抑えられるので、コスト効率を高めるために必要です。
大量に輸送する
北海道における輸送の特徴には、大量に輸送することも挙げられます。北海道は大量の農作物や海産物、畜産物を生産しているので、本州へ大量に輸送する手段が必要不可欠です。
特に鉄道やフェリーは大量輸送手段として重要な役割を果たしています。鉄道はコンテナを積み重ねて一度に大量輸送できるため、長距離輸送に適しています。フェリーはトラックごと大量の貨物を運べるので、輸送力が高い上に効率も良いです。
北海道から本州への輸送手段は?

北海道から本州への輸送手段には、以下の3つがあります。
- 海上輸送
- 鉄道輸送
- 航空機輸送
それぞれについて詳細を見ていきましょう。
海上輸送
北海道から本州の輸送で最も重要な役割を担っているのが、海上輸送です。海上輸送は大量輸送が可能な上にコストも低いため、農産物や魚介類、生活物資など、幅広い品目が日々運ばれています。
特にRORO船は、海上輸送において非常に重要です。RORO船とは、トラックやトレーラーなどの車両が自走で乗り降りできるように、ランプウェイと呼ばれる傾斜路を備え付けた船です。RORO船はトラックやトレーラーを運転手ごと運べるので、本州に着いてから荷物の積み替えなしで、すぐにトラック輸送を開始できます。
海上輸送は、一度に大量の貨物を運べるため、燃料消費効率が非常に良いです。コストパフォーマンスだけでなく環境負荷の低減にもつながるため、北海道の輸送で欠かせない存在です。一方で、天候の影響を受けやすく、輸送に時間がかかるデメリットもあります。
鉄道輸送
鉄道輸送も、北海道から本州の輸送では欠かせません。主に北海道と本州をつなぐ青函トンネルを経由して行われ、安定した輸送力が強みです。
天候の影響を受けやすい海上輸送に比べ、鉄道輸送は比較的天候の影響を受けずに安定して運行できます。コンテナを利用することで、積み替え作業の手間を減らし、トラックなど他の輸送手段との連携もスムーズに行えます。
鉄道輸送は、コンテナを利用して、重量のある貨物をはじめとする大量の貨物を輸送するのが得意です。そのため、北海道で生産される農産物や、加工食品、紙・パルプ製品などが主に鉄道で運ばれています。ただし、海上輸送に比べてコストが高くなるほか、輸送できる地域が鉄道網の範囲に限られるデメリットがあります。
航空機輸送
北海道から本州への輸送手段の最後は、航空機輸送です。航空機輸送は、何よりも速達性が求められる貨物に適しています。新千歳空港をハブとして、生鮮食品や医薬品、電子部品など、緊急性の高い貨物や高価な商品を、日本各地へ迅速に届けられます。
特に、北海道が誇るウニやカニ、メロン、アスパラガスなどの高付加価値な生鮮品は、鮮度が命です。収穫・水揚げから24時間以内に消費地に届ける必要があるので、保冷設備を備えた航空貨物便を利用して迅速に輸送します。航空輸送は他の手段と比べて輸送コストが高くなるので、必要なものにだけ利用されています。
北海道での輸送リスク

北海道は本州と隔てられており、面積が広くて発展している都市の場所にばらつきがあるため、様々な輸送リスクが伴います。北海道での輸送リスクは、以下の3つです。
- 海上の荒天による影響が大きい
- 物流拠点が分散されている
- 迂回ルートが少ない
それぞれについて、詳しく確認していきましょう。
海上の荒天による影響が大きい
北海道での輸送リスクの1つ目は、海上の荒天による影響が大きいことです。北海道は、三方を海に囲まれているため、海上の荒天による輸送リスクに常に直面しています。特に冬場は、日本海やオホーツク海で発達した低気圧により、高波やしけが発生しやすく、フェリーやRORO船の欠航が頻繁に起こります。
海上輸送の遅れは、北海道の経済に大きな損失をもたらすものです。農産物や水産物、乳製品などの生鮮品は、輸送の遅れがそのまま品質の低下を招きます。本州から運ばれてくる生活物資や工業製品なども滞り、地域経済や住民生活にも影響が及ぶので、余裕をもった輸送計画を立てるなどの対策が必要です。
物流拠点が分散されている
物流拠点が分散されていることも、北海道での輸送リスクとして挙げられます。北海道の物流拠点は、札幌を中心としつつも、函館、苫小牧、釧路、帯広など、道内各地に分散しています。拠点が分散しているので、物流コストの増加や効率性の低下がリスクです。
北海道では、生産されたものを効率的に集荷・出荷するために、それぞれの地域が漁業、農業、酪農などの独自の産業を持っています。各拠点から消費地や港へ物資を運ぶには、長距離の陸上輸送が必要ですが、広大な北海道では、輸送ルートが複雑になり、スケジュールの調整が複雑です。生産者と輸送者が連携し、効率的なルートを模索する必要があります。
迂回ルートが少ない
北海道の輸送リスクの最後は、迂回ルートが少ないことです。北海道と本州を結ぶ輸送ルートは、青函トンネルを経由する鉄道輸送と、複数の港を結ぶ海上輸送が主であり、災害時やトラブル発生時の迂回ルートが限られています。
例えば、青函トンネル内で事故や自然災害が発生した場合、鉄道輸送が完全にストップする可能性があります。同様に、海上輸送でも、特定の港でストライキや設備の故障が発生すると、その航路を利用しているすべての物流が影響を受けます。代替ルートを確保するなどの対策が必要ですが、地理的な制約があるため、北海道の物流の根本的な課題となっています。
北海道からの輸送なら日新運輸工業にご相談ください

日新運輸工業では、フェリー輸送や鉄道輸送の業務委託やアウトソーシングを受注しております。トラック輸送も行っているので、両者の利点を理解した上でより効果的に北海道での輸送のサポートができます。
北海道での輸送手段を検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。電話やメールにて、見積もり・お問い合わせを承っております。
国内貨物輸送の手間やコストにお困りの人は、日新運輸工業におまかせください!
以下サービスページより国内貨物輸送の問い合わせができますので、ご相談お待ちしております。
まとめ

この記事では、北海道の貨物輸送について解説しました。北海道は本州から陸路で繋がっておらず、広大な土地の様々な場所に拠点となる都市があるため、複数の輸送手段を組み合わせることが必要です。
北海道から本州への輸送手段は、以下の3つです。
- 海上輸送
- 鉄道輸送
- 航空機輸送
海上輸送は特に天候に左右されやすいですが、複数の輸送手段を検討して代替案を準備しておくことで、安定的な輸送を確保できます。北海道の地理的な特性を生かして、より効率的に貨物輸送を行いましょう。
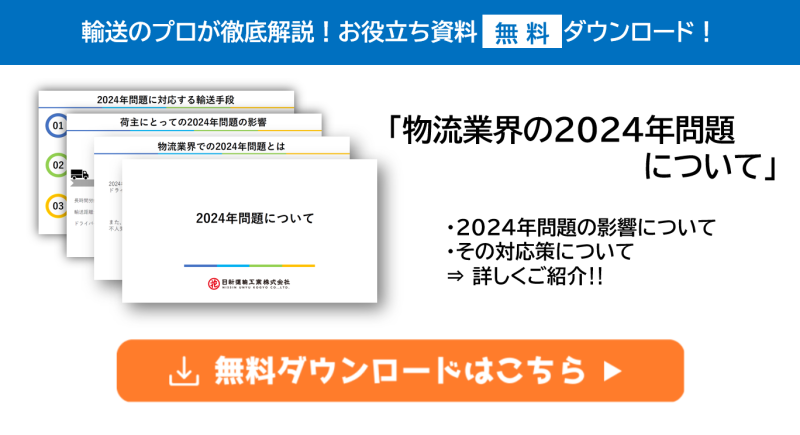
監修者
浜田 智弘
日新運輸工業株式会社 運輸部 部長
国内物流の現場で指揮を執り、トラック・鉄道・フェリーを組み合わせた最適な輸送提案や、「2024年問題」への実務対応に精通。「マルハナジャーナル」での執筆を通じ、物流業界の課題解決にも尽力している。「感謝と恩返し」を信念に、困難な物流課題にも粘り強く向き合い続けている。