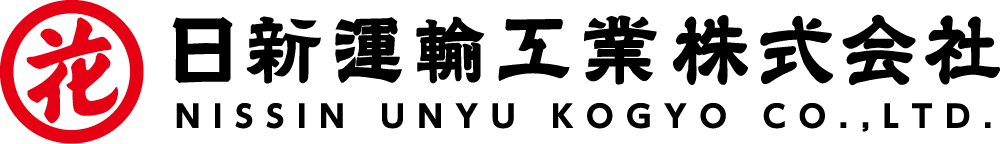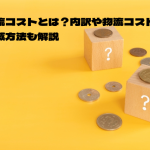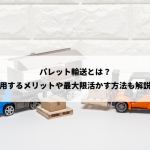長距離トラックの年間走行距離が気になる人も多いのではないでしょうか。長距離トラックと一口に言っても、運行方法によって走行距離が大きく異なります。
この記事では、長距離トラックの走行距離について解説します。物流業界で話題となっている2024年問題の影響や対策についても解説するので、ぜひ内容を確認してみてください。

長距離トラックの年間走行距離は?

長距離トラックの年間走行距離は、運行形態によって大きく変動しますが、一般的な大型トラックの平均走行距離を大幅に上回る傾向にあります。特に連続して運行する日数が多くなればなるほど、走行距離は伸びます。
運行パターンで多いのは、以下の2つです。
- 2日運行
- 5日運行
それぞれの年間走行距離について、詳しく確認していきましょう。
2日運行
「2日運行」とは、出発から帰着まで2日間を要する運行パターンであり、年間走行距離は10万キロメートルを超えます。1日あたり450キロメートルから500キロメートルの走行距離で、東京と大阪の間を往復する場合などが挙げられます。
2日運行では、1日目で往路を走行後、宿泊してから2日目に復路を走行するパターンが多いです。 改善基準告示では、一般的な1日の休息時間が9時間を下回ってはいけないと定められていますが、宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合、週2回までであれば継続8時間以上を休息の最低時間とすることができます。
ただし、休息期間が2日とも9時間を下回った場合は、その運行が終了した後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があります。そのため、1週間の運行回数を2回とする場合が多いです。
5日運行
「5日運行」とは、出発から帰着まで5日間かかる運行パターンであり、年間走行距離は12万キロメートルを超える場合がほとんどです。北海道や東北から九州までなど、日本列島を縦断する片道1,000キロメートル以上の輸送に利用されます。
5日運行では、2日間かけて往路を走ってから3日目に荷下ろしと積み込みをし、また2日間かけて復路を走るパターンが基本です。国土交通省告示では、出発地点を出てから再び帰ってくるまでの全期間を6日以内に収めなければならないと定められているため、拘束時間の規制内で最大限の稼働となります。
2024年問題が長距離トラックの走行距離に与える影響

長距離トラックの走行距離は、2024年問題の影響を大きく受けると言われています。「2024年問題」とは、2024年4月から労働時間の新基準が適用されることで、ドライバーの労働時間が短くなり、運行能力の低下や人手不足が懸念されている問題です。
2024年問題が長距離トラックの走行距離に与える影響は、以下の3つです。
- 1人あたりの走行距離が短縮される
- 中継輸送が増える
- ドライバーの収入が減少する
それぞれについて詳しく解説していきます。
1人あたりの走行距離が短縮される
2024年問題の最大の影響は、1人あたりの走行距離が短縮されることです。労働時間の規制が強化されるため、1日の拘束時間や運転時間が短くなり、長距離輸送が難しくなります。
2024年4月以前は、年間の時間外労働の上限がありませんでしたが、法改正後は年間960時間の上限が適用されています。これにより長時間残業ができなくなるので、1回での長距離輸送は困難です。
具体的には、法改正前は1日で片道500キロメートル以上の走行が可能でしたが、現在は500キロメートル以上の場合、片道に2日間かかります。2日運行で輸送していた区間が3日運行になり、輸送能力が低下します。
中継輸送が増える
中継輸送が増えることも、2024年問題が長距離トラックの走行距離に与える影響の1つです。1人あたりの運行時間が短くなるので、途中で交代して2人体制で運転する必要があります。
一般的には、関西や中京エリアに中継地点を設け、ドライバーが交代で運転するか、荷物を別のトラックに積み替えます。2人分のドライバーの人件費が発生するので、物流コストの増加が顕著です。
ドライバーの収入が減少する
2024年問題が長距離トラックの走行距離に与える影響には、ドライバーの収入が減少することも挙げられます。長距離ドライバーの給与には、走行距離に応じた「長距離手当」が含まれていることが多いですが、法改正で長距離輸送が難しくなり手当が少なくなります。
ドライバーの収入が減少すると、離職者が増え人手不足が深刻化する可能性も高まるでしょう。輸送会社は基本給の引き上げや運行の効率化を行い、ドライバーの収入を維持する必要があります。
今後の長距離トラック輸送のポイント

2024年問題の影響を踏まえて、今後の長距離トラック輸送では以下を行うことがポイントです。
- 業務を効率化する
- 運行方法を見直す
- モーダルシフトを活用する
それぞれについて、詳細を見ていきましょう。
業務を効率化する
今後の長距離トラック輸送の1番のポイントは、業務を効率化することです。業務を効率化することで、短い労働時間でも今までどおりの輸送を行うことが可能になります。
長距離ドライバーの長時間労働は、納品先での待機時間や手作業の荷役時間が原因の1つです。これに対し、たとえばトラック予約システムを導入してトラックの入庫時間を予約制にすることで、ドライバーの待機時間を大幅に削減できます。
荷役時間の短縮には、荷物をパレットにまとめてフォークリフトなどで一括して積み下ろすことが有効です。他にも、デジタル技術やAIを活用して運行計画を最適化することで、従来より効率的なルートで輸送できます。
運行方法を見直す
今後の長距離トラック輸送のポイントには、運行方法を見直すことも挙げられます。複数の輸送会社や荷主が連携し、同じ方面への貨物を1台のトラックにまとめて輸送することで、少ないドライバーでも従来と同じように輸送できます。
他にも、ドライバーが日帰りで運行できるように、中継輸送を導入することも効果的です。拘束時間や運転時間を短縮できるためドライバーの労働環境が改善され、新たな人材の雇用や離職率を下げることが期待できます。
モーダルシフトを活用する
モーダルシフトを活用することも、今後の長距離トラック輸送のポイントです。モーダルシフトによって一度に大量の貨物を輸送できるので、トラックの輸送能力不足を補えます。
モーダルシフトとは、トラックでの輸送を船舶や鉄道に切り替えることを指します。船舶や鉄道は大型トラックの数倍の荷物を運べるので、単位量あたりの輸送コストが少なくなる上、トラックドライバーの長距離運行の負担を軽減することも可能です。
長距離トラック輸送なら日新運輸工業におまかせください

日新運輸工業では、トラック輸送の業務委託やアウトソーシングを受注しております。輸送のプロとして培ってきたノウハウがあるので、より効率的に長距離輸送を行えます。フェリー輸送や鉄道輸送にも対応しているので、最適な輸送方法をご提案できます。
長距離トラック輸送をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。電話やメールにて、見積もり・お問い合わせを承っております。
国内貨物輸送の手間やコストにお困りの人は、日新運輸工業におまかせください!
以下サービスページより国内貨物輸送の問い合わせができますので、ご相談お待ちしております。
まとめ

この記事では長距離トラックの走行距離について解説しました。長距離トラックの年間走行距離は、運行方式によって大きく異なります。
今後の長距離トラック輸送のポイントは、以下の3つです。
- 業務を効率化する
- 運行方法を見直す
- モーダルシフトを活用する
2024年問題により走行距離の減少が懸念されていますが、これまでの輸送を見直すことで今までの輸送量を維持できます。法改正に合わせた長距離トラック輸送を行いましょう。
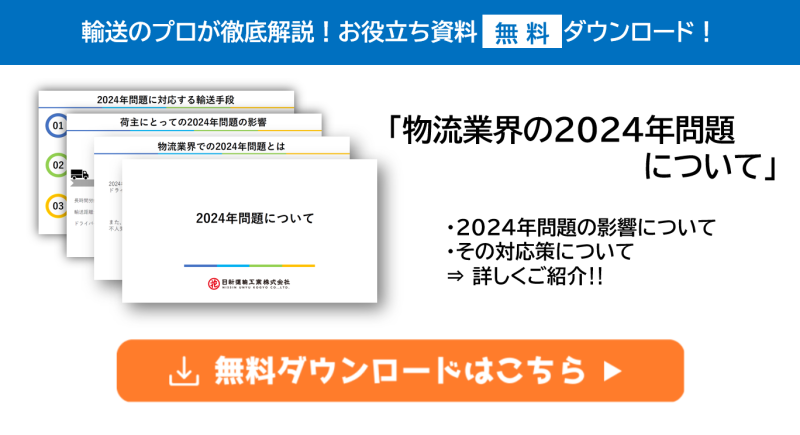
監修者
浜田 智弘
日新運輸工業株式会社 運輸部 部長
国内物流の現場で指揮を執り、トラック・鉄道・フェリーを組み合わせた最適な輸送提案や、「2024年問題」への実務対応に精通。「マルハナジャーナル」での執筆を通じ、物流業界の課題解決にも尽力している。「感謝と恩返し」を信念に、困難な物流課題にも粘り強く向き合い続けている。