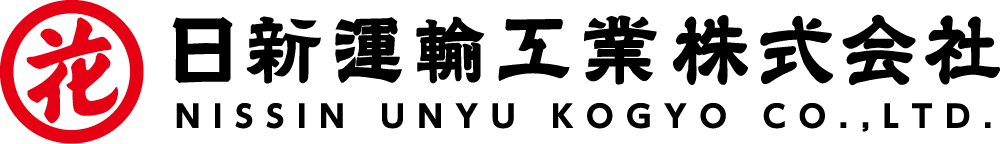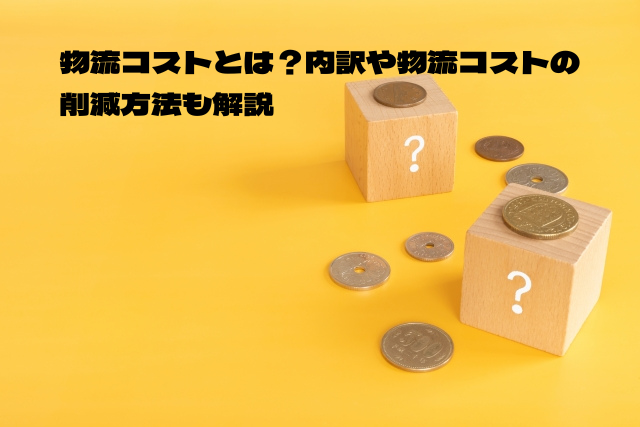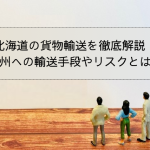物流コストとは何か気になっている人も多いのではないでしょうか。物流コストとは、商品を顧客の元に届けるまでにかかる費用を意味します。
この記事では、物流コストについて解説します。内訳や物流コストの削減方法も紹介するので、ぜひ最後まで確認してみてください。

物流コストとは

物流コストとは、商品を顧客のもとへ届けるまでに発生する総費用のことを指します。輸送費・荷役費・倉庫保管費・梱包費・人件費などが主な項目です。これらは原価全体の中でも大きな比重を占め、改善の積み重ねが経営効率の差につながります。
物流コストは燃料価格や人件費の変動に影響されやすく、日々の運用次第で収益を大きく左右します。トラックの積載効率を高めたり、ルート最適化ソフトを活用したりすることで、走行距離や燃料消費の削減が可能になります。また、在庫の回転率を上げて保管コストを抑えることも効果的です。
物流コストの見直しは、単なる節約ではなく、企業の競争力を高める取り組みです。最近では、データによる見える化やアライアンス輸送(複数企業が協力して輸送資源を共有・効率化する仕組み)が注目を集めています。AIを活用して運行状況を管理し、複数企業が輸送を共有することで、コストと環境負荷の両面を最適化できます。
物流コストの内訳

物流コストの内訳は以下に分けられます。輸送・配送にかかる費用、荷役作業にかかる費用、倉庫での保管にかかる費用、管理や人件費などの費用、梱包・包装にかかる費用です。
それぞれ詳細を確認していきましょう。
輸送・配送にかかる費用
輸送・配送にかかる費用は、物流コスト全体の中でも最も大きな比率を占める重要な項目です。商品を生産地や倉庫から取引先、店舗、顧客のもとに届けるまでに発生するすべての移動費用が該当します。
トラック・鉄道・船舶・航空機などの輸送手段にかかる料金の他にも、燃料費や高速料金、車両の維持費、ドライバーの人件費なども含まれます。これらは燃料価格や人手不足、天候などの環境要因に左右されやすく、常にコスト管理が必要です。
効率化のためには、配送ルートの最適化や積載率の向上、他社との共同配送の導入がおすすめです。小さな改善の積み重ねが、物流コスト削減に直結します。
荷役作業にかかる費用
荷役作業にかかる費用とは、商品の積み込み・積み下ろし・仕分け・移動など、物理的な取り扱い作業に伴う費用のことです。
人の手作業にかかる人件費、フォークリフトなどの機械の燃料・メンテナンス代、作業場の整備コストも含まれます。荷役作業は倉庫や港湾、物流拠点など至るところで発生し、この効率性が全体のリードタイムとコストを大きく左右します。
自動化設備やピッキングロボットの導入、荷姿の統一化などで作業時間を減らせば、コスト削減になるでしょう。出荷回数の見直しや物流拠点の統合など、運用面の改善も有効的です。
倉庫での保管にかかる費用
倉庫での保管にかかる費用は、商品を一時的に保管する際に発生するコストで、物流の安定運用に欠かせません。
主な内訳は倉庫賃料、照明・空調などのエネルギー費、設備維持費、保険料、セキュリティ費などです。また、温度や湿度管理を要する商品では特別な保管設備が必要となり、費用が一層増加します。
コストを抑えるには在庫回転率を上げ、必要なスペースだけを確保することが重要です。AIを活用した在庫予測やデータ分析により、過剰在庫や品切れを防ぎ、効率的な保管が実現できます。シェア倉庫や外部委託の活用も効果的です。変動需要への柔軟な対応も可能になるため、ぜひ検討してみてください。
管理や人件費などの費用
管理費や人件費は、物流業務を円滑に運営するための費用です。物流部門の従業員や管理職の人件費、派遣スタッフの給与、教育研修費、福利厚生費などが含まれます。加えて、情報システムの導入・運用費や事務所の光熱費、セキュリティ管理・法令対応などの間接コストも対象です。
業務量や人員構成によって変動するため、ITツールや自動化システムによる標準化が有効です。システム連携を強化し、データ管理や帳票処理を効率化することで、生産性を上げながら人件費を抑えることができます。
梱包・包装にかかる費用
梱包・包装費用は、商品を安全に届けるために必要なコストです。ダンボール、緩衝材、テープ、ラベルなどの資材費や梱包作業の人件費が該当します。外装は商品の保護だけでなくブランド価値にも関わるため、品質を落とさず効率化を図る工夫が求められます。
過剰包装をなくし、最適なサイズ・素材を選定することで、資材費と廃棄コストを削減できるでしょう。現在は、リサイクル可能な材料や環境負荷の少ない資材を取り入れる企業も増えています。梱包設計を標準化することで輸送効率も向上し、結果的に輸送費削減にもつながる可能性があります。
物流コストの比率について

物流コストの構成割合は業界や輸配送の仕組みによって変わります。一般的には輸送費が全体の約6割を占め、次いで保管費がおよそ2割、その他の荷役費・管理費・梱包費などがそれぞれ数%から1割程度の比率となります。輸送費が高くなりやすいのは、燃料代や人件費、車両の維持費といった変動要因が多く、配送距離や便数による増減が大きいためです。
製造業で全国規模の配送を行う場合は輸送費の割合がさらに高まり、製品価格にも直接影響します。在庫量が多い業態では保管費の比率が増えることが多いでしょう。荷役費は商品形状やサイズ、出荷頻度によって左右され、多品種少量出荷では上昇しやすいです。また、管理費やシステム費はIT化によって一時的に額が増える場合もありますが、効率化の進展で比率が抑えられる可能性もあります。
こうした比率の把握は、改善の優先順位を決めるうえで欠かせません。コスト構造を数値で明確化することで、無駄の洗い出しや投資判断が容易になり、長期的な物流コスト削減へとつながります。
物流コストが高騰する要因

物流コストが高騰する要因は、燃料価格の上昇、ドライバー不足、積載効率の低下や輸送回数の増加が考えられます。それぞれ詳細を確認していきましょう。
燃料価格の上昇
コストが上昇する主な要因の一つは、燃料価格の上昇です。燃料費はトラック輸送をはじめ、航空便や海上輸送などあらゆる輸送手段の基本コストに直結しており、収益や経営計画に大きな影響を与えます。
燃料価格が上昇する背景には、国際的な原油価格の悪化や株価の変動、カーボンニュートラル政策(脱炭素化を進める政策)によるエネルギー転換があります。日本はエネルギー資源の多くを輸入に頼っているため、海外情勢に影響を受けやすいです。結果的に燃料コストの上昇が物流業界全体の負担となっています。
燃料コスト対策としては、燃費性能の高い車両への更新やエコドライブの推進、省エネタイヤの導入が効果的です。また、共同配送や鉄道・船舶へのモーダルシフトなど、燃料使用を抑えた輸送体制への転換が将来のコスト安定化につながるでしょう。
ドライバー不足
ドライバー不足も物流コストが高騰する要因です。ドライバー不足は、2024年問題を契機とした労働環境の見直しや、少子化による労働人口減少といった社会構造の変化が背景にあります。
長時間労働や過密スケジュールといった過酷な労働環境が続いたことから、若年層の新規参入が減少し、高齢化が進んでいます。法改正により、運転可能時間が制限されたことで、輸送量の確保が困難です。特に地方ではドライバーの採用が追いつかず、配送の遅延や遅延回数の減少が発生し、サービスの品質の維持も課題となっています。人手確保のために人件費が上昇し、運賃や委託費などのコスト全体が増えている状況となっています。
ドライバー不足対策としては、労働環境の改善と多様な人材確保が重要です。自動積み下ろしシステムの導入でドライバーの作業負担を軽減したり、労働体制の見直しをしたりすることで職場環境も整います。女性やシニアの積極的な採用や柔軟な勤務制度を作ることで、持続可能な輸送体制が構築できるでしょう。
積載効率の低下や輸送回数の増加
物流コストが高騰する一因として、積載効率の低下や輸送回数の増加も挙げられます。EC市場の拡大や個別配送の増加、配送時間指定など、多様化された配送希望があるためです。
これまでは1台のトラックで多くの荷物をまとめて運ぶことが主流でしたが、現在は消費者のニーズが多様化し、小口配送や納期対応が多い状況です。1回あたりの積載量が減り、同じ商品量を運ぶために必要な便数や車両台数が増加しています。そのため、燃料費・人件費・車両維持費などの負担が大きくなっています。
改善策としては、複数企業やエリア間での共同配送や、鉄道・船舶とトラックを組み合わせたモーダルシフトの推進が有効です。配車や運行計画の最適化のためにAIやデジタルツールを積極的に活用することも効果的でしょう。効率的なルート設計や輸送計画が実現し、無駄のない輸送計画を組むことが可能になります。
物流コストの削減方法とは

物流コストの削減方法は、物流拠点を集約すること、アウトソーシングを活用すること、人件費や管理費を見直すことです。それぞれ詳細を確認していきましょう。
物流拠点を集約する
物流コスト削減を実現するための有効な方法は、物流拠点を集約することです。物流拠点を集約することで管理・人件費や倉庫運営費、保管料などの固定費を削減できます。
複数の倉庫や配送拠点を分散運用している場合、管理コストや輸配送ルートの複雑化を招きます。物流拠点が絞られることで配送ルートの最適化やスケジュール短縮が可能となり、手数料の削減や燃料費の節約につながるでしょう。配送効率が上昇することで、ドライバーの軽減負担にもなります。
実際に拠点集中を実施した企業では、配送便数の削減によるCO2排出量の削減や、作業の省力化によるコストダウンが報告されています。自動化技術やITシステムと連携した拠点集約が要となるでしょう。
アウトソーシングを活用する
物流コスト削減を持続的に進めたい企業には、アウトソーシングの活用が効果的です。物流業務のすべてを自社で行うと、人件費・設備費・車両維持費などの固定費が増大し、変動に応じた柔軟な対応が難しくなります。物流専門の会社へ委託することでコストを変動費化でき、繁忙期・閑散期にも対応しやすくなります。
倉庫運営や配送業務をアウトソーシングすることで、自社は浮いた人的・資金的余力を最新の自動化設備や効率的な輸送ネットワークへの投資に充てることができます。また、専門業者のノウハウにより、誤出荷や納期遅延の防止、サービス品質の安定化も期待できるでしょう。委託コストを明確に設定し、成果指標で管理すれば、コストと品質のバランスを維持しながら運用できます。
信頼できるパートナーの選定と定期的な契約見直しを行えば、物流コスト削減の効果を中長期的に持続させることが可能です。物流コストの変動費化は、今後の企業経営における重要な戦略の一つとなるでしょう。
人件費や管理費を見直す
人件費や管理費の見直しはコスト削減に欠かせないポイントです。多くの企業が拠点ごとの管理者や事務スタッフの人数を調整し、管理関連の経費を大幅に抑えています。
物流拠点を複数から1か所に集約することで、ドライバーの労働時間が短縮され、物流センターの維持管理費を軽減することが可能です。ITシステムの導入により配車や在庫管理を効率化している事例も増えています。
配送ルートや納品スケジュールを見直すことも重要です。無駄な稼働や残業を減らし、適正な労働時間管理を推進できます。働きやすい環境を整えることで離職率の低下も期待でき、結果として採用・教育コストの抑制にもつながるでしょう。
物流コスト削減でお困りの際は日新運輸工業にお任せください

昨今の燃料価格や労働コストの上昇を受け、物流費用の増大に悩む企業が増加しています。収益性を維持するためには、現状のコスト構造を正確に把握し、戦略的な改善アプローチを実行することが不可欠です。
物流コスト削減でお困りの際は日新運輸工業にお任せください。無理なくコストを抑えた最適な物流体制をご提案し、サポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。メールでのお問い合わせも可能です。
国内貨物輸送の手間やコストにお困りの人は、日新運輸工業におまかせください!
以下サービスページより国内貨物輸送の問い合わせができますので、ご相談お待ちしております。
まとめ

この記事では、物流コストについて解説しました。物流コストとは、商品を顧客に届けるまでの一連の過程で発生する費用のことを指します。
物流コストを削減する方法は、以下の通りです。
- 物流拠点を集約する
- アウトソーシングを活用する
- 人件費や管理費を見直す
さまざまな施策を組み合わせて実践することで、コストの最適化だけでなく業務全体の生産性向上にもつながります。継続的に見直しを行い、効率的で持続可能な物流体制を確立していくことが重要です。
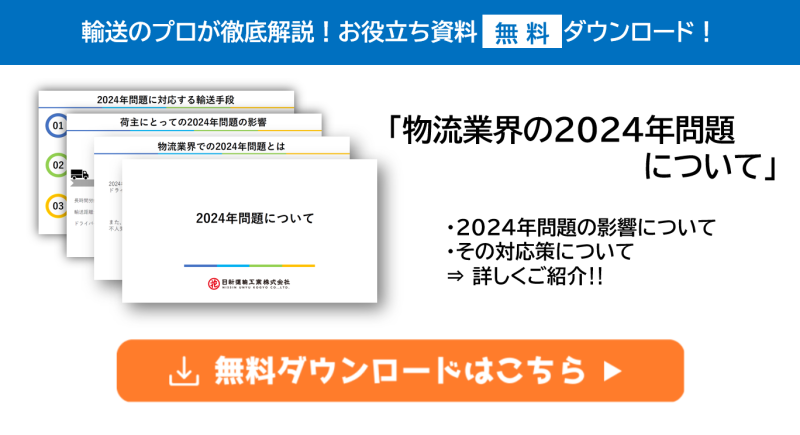
日新運輸工業のプロフェッショナル紹介
浜田 智弘(運輸部 部長)
経験と専門性
日新運輸工業 運輸部にて6年9ヶ月の経験を持ち、部長として国内物流業務を統括。管理職として多数の運輸案件を指揮し、物流の最適化に取り組んでいます。
専門領域と実績

国内物流のエキスパートとして、以下の分野に精通:
トラック輸送の専門知識
- トラック輸送のメリット・デメリット分析
- 特殊車両輸送(ポールトレーラー等)の実務
- トラック運賃の適正化と運送契約
- 機械輸送における安全管理
鉄道・船舶輸送の活用
- JR貨物輸送の実務と活用方法
- フェリー輸送の効率的な利用
- トラックと鉄道の輸送比較
- モーダルシフトの推進と実装
2024年問題への対応
- 物流業界の働き方改革と実務対応
- 長距離輸送における課題解決
- 運送業界の法令遵守と効率化の両立
- 輸送能力維持のための戦略立案
その他専門分野
- 金属スクラップの輸送管理
- 深穴切削加工(BTA)製品の物流
- 物流業界の法規制対応
情報発信と業界課題への取り組み
「マルハナジャーナル」にて、国内物流に関する専門記事を15本以上執筆。特に2024年問題など、業界が直面する課題について実践的な解決策を提示しています。主な執筆テーマ:
- 2024年問題が長距離輸送に与える影響と対策
- トラック輸送の種類と特徴
- モーダルシフトの実践方法
- 運輸業界の現状と課題
- 効率的な輸送方法の選択
サービス理念
「感謝と恩返し」を信念とし、コミュニケーションを重視した業務運営を実践。「忍耐とねばり強さ」を持って困難な物流課題にも対応し、お客様から「よく対応していただき助かっています」という評価をいただいています。
チーム内外で助け合いながら、事業をさらに成長させることを目指しています。
継続的な学習と成長
物流業界のデジタル化に対応するため、ChatGPTなどAI技術の研修に積極的に参加。また、物流関連の法令改正説明会にも定期的に参加し、最新の規制動向を把握しています。
今後は倉庫建設をはじめとする新規事業にも取り組み、お客様により幅広い総合物流サービスを提供できる体制を整えていく予定です。
日新運輸工業の専門性

日新運輸工業では、椎木・浜田両名をはじめとする経験豊富な専門スタッフが、国際物流と国内物流の両面から総合的な物流ソリューションを提供しています。
- 国際部:通関士が多数在籍し、輸出入通関手続きから国際輸送まで一貫対応
- 運輸部:トラック・鉄道・船舶を組み合わせた最適な輸送手段を提案
お客様の物流課題に対して、専門知識と豊富な経験を活かした実践的なソリューションを提供し、常に改善と成長を続けながら、持続可能な物流の実現を目指しています。
執筆記事は「マルハナジャーナル」で公開中:https://nissin21.co.jp/マルハナジャーナル/